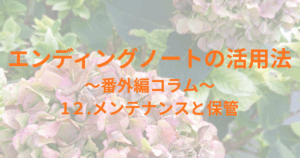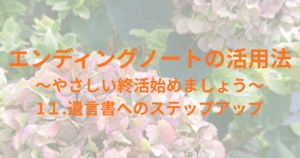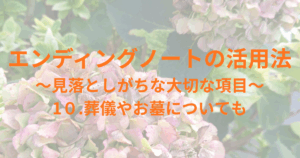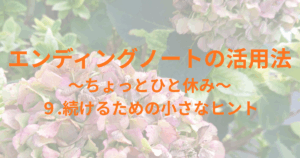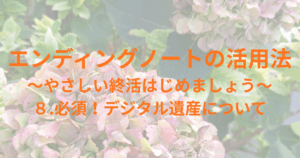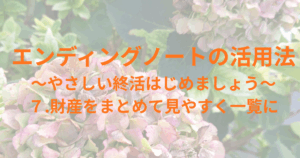「法定相続証明制度」とは
本制度は、相続人から相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、戸除籍謄本等の束を登記所に提出していただき、一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認した上で、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというものです。
(法務局サイトより引用)
相続により不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないとして、令和6年4月1日以降、相続登記の申請が義務化されました。
本来であれば、所有する不動産の所在地を管轄する法務局に対し、亡くなった方の相続関係を証明する書類として、戸除籍謄本等の原本の束を提出しなければなりません。時にはかなりの枚数になるこれらの書類を集め、揃え、各所に提出するのは大変です。
ところが、法定相続情報一覧図の写しを発行してもらえば、公的に相続関係を証明する書類として、こちらを戸除籍謄本等の束の代わりに相続登記に利用することが出来ます。もう重たい戸除籍謄本等の束をあちこちの法務局に出す必要がなくなるのです。
法定相続情報証明制度の利用方法
まず利用前に確認しておきたいことは、この制度の利用を申し出ることが出来る人は、相続人に限られるということです。遺言によって受遺者となった方や、遺言執行人は制度の利用申出は出来ません。
また、この申出は、申出人(相続人の一人)からの委任により、代理人に依頼することが出来ます。代理人は親族のほか、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家にも依頼することが出来ます。
被相続人(亡くなった方)の相続人を特定するために必要な戸除籍を収集します。
被相続人の出生から死亡までの戸除籍をたどり、相続人の現在の戸籍と合わせて全て収集します。
被相続人(亡くなった方)及び、戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成します。
ここには被相続人が亡くなった時点において、実際に相続人となっている方のみを記載します。
申出書に必要事項を記入し、STEP1で用意した戸除籍等の束、STEP2で作成した法定相続情報一覧図を合わせて、登記所に申出をします。
申出をする登記所は以下のどこでも可能です。
- 被相続人の本籍地(死亡時の本籍地)
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の所在地
- 被相続人名義の不動産の所在地
なお郵送による申出、及び交付の希望も可能です。
窓口での受け取りの際は、申出書に記載した申出人と同じ住所、氏名が書かれた身分証明書を持参します。
法定相続情報一覧図の写しの活用
この法定相続情報一覧図は、5年間(申出日の翌年から起算)保存されるので、その間であれば写しの再交付が可能です。ただし、再交付の申出が出来るのは当初の申出書に「申出人」として氏名を記載した方のみで、申出場所は当初の申出をした登記所となります。
また、この法定相続情報一覧図の写しは、不動産の相続登記だけではなく、金融機関、生命保険、年金、自動車関連、相続税の申告等、他の相続関係手続にも利用することが出来るというメリットがあります。
各所に重たい戸除籍謄本等の束を持ち歩き、時間をかけて確認してもらう間、延々待ち続ける…といったストレスから解放されます。
まとめ
一度作成してしまえば、被相続人が亡くなった時点での相続関係が一目で分かり、しかも公的に証明されている便利な書類が「法定相続情報一覧図の写し」です。
申出までの各段階は面倒な作業もありますが、そこは書類作成の専門家である行政書士にお任せして、後々のことまで考えた相続登記手続きの効率化を図りましょう!
お問い合わせ、ご相談はお気軽に!
行政書士わかぞの事務所