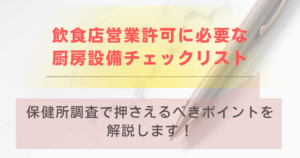飲食店を開業してしばらく経つと、「夜の時間帯にも営業を延ばしたい」「お酒中心のバー営業をやってみたい」と考える方も多いでしょう。そんな時に関係してくるのが「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」です。今回は、この届出の対象となるお店の条件や、店舗に求められる基準をまとめてご紹介します。
どんなお店が届出の対象になる?
深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になるのは、『午前0時以降にお酒をメインに提供して営業するお店』です。
たとえば、居酒屋やバーなどで深夜もアルコールを提供し続ける場合が該当します。「午前0時以降の深夜営業」そして「アルコールメインの提供」この二つがポイントです。
一方で、午前0時までに閉店するお店や、食事がメインでお酒は軽く添える程度、という場合は、通常の飲食店営業許可のままで問題ありません。
(夜中も空いているラーメン店や定食屋、ファミレスなどは食事の提供がメインですので、アルコールの提供があったとしても該当しないのです。)
届出を出すタイミングと提出先
届出は、営業を始める10日前までにお店の所在地を管轄する警察署(生活安全課)に提出します。
保健所からの飲食店営業許可とは別に、警察への届出が必要になる点に注意しましょう。
主な提出書類
・営業開始届出書(所定の様式)
・営業の方法を記載した書類(所定の様式)
・店舗の平面図
・住民票や誓約書など、申請者に関する書類
・店舗の使用承諾書(賃貸物件の場合)
・飲食店営業許可書の写し
・メニュー表 等…
警察署によって、求められる書類は少しずつ異なるかも知れません。事前に確認して行かれることをおすすめします。
営業できる場所の制限にも注意
深夜酒類提供飲食店は、すべての地域で営業できるわけではありません。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法)によって、営業が制限される区域があります。
【深夜営業が可能な用途地域】
・商業地域
・近隣商業地域
・準工業地域 等…
逆に住宅街(第1種、第2種低層住居専用地域など)では深夜営業は認められません。このため、物件選びの段階で用途地域を確認しておくことがとても大切です。
店舗の設備・構造にも一定の基準があります
警察署に届出を出す際に確認される主な基準は、以下の通りです。
【チェック項目】
・照度…客室の明るさは20ルクス以上(新聞が読める程度)
・面積…客室の床面積は9.5㎡以上であること(各室が一室の場合、制限はない)
・見通し…客室は全体が見通せる構造であること(間仕切り高さ1m以上のもの、個室に注意)
・出入口…外から営業の様子が分かるようにする(完全に閉鎖された構造は不可)
・防音…地域によっては騒音対策の指導を受ける場合あり
※特に「照度」と「見通し」は重要です!基準を満たしていないと、届出が受理されなかったり、警察署による現地確認が行われる可能性もあります。
届出をしないまま営業すると風営法違反に
「保健所の飲食店営業許可があるから大丈夫」と思い込んで、深夜営業を始めてしまうケースもありますが、深夜酒類提供の届出をしていない場合は、風営法違反に当たります。
営業停止や行政指導の対象になることもありますので、営業スタイルを変更する際は必ず届出等が必要かそうでないかを確認しましょう。
まとめ:将来の展開を見据えて準備を
最初は通常の飲食店営業許可だけで始めても、将来的に営業時間を延ばしたり、バー営業を始めたりする場合は、この届出が必要になります。
開業当初から大まかにでも将来、どんな営業スタイルにしていくかを見据えておくと、基準を満たすために後から改修工事をしたり、場所を移転したり…と言ったハードルを取り除いておくことができますね。
具体的には、店舗を借りる段階から「用途地域」「店の構造基準」「照明設備」を意識しておくと言ったことです。
行政書士としては、届出書類の作成や図面の確認、管轄警察署との事前相談もお手伝いできます。
新しい営業スタイルを始めてみようと思われる方。
通常の営業に加え、メニュー開発、試作、宣伝、スタッフの増員など、やることが大幅に増えるでしょう。そんな時は、ぜひ行政書士を頼ってみてください。手続きにかかる時間を節約し、その分を店長・オーナーとしての本分にご注力いただけると思います。
お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ
行政書士わかぞの事務所