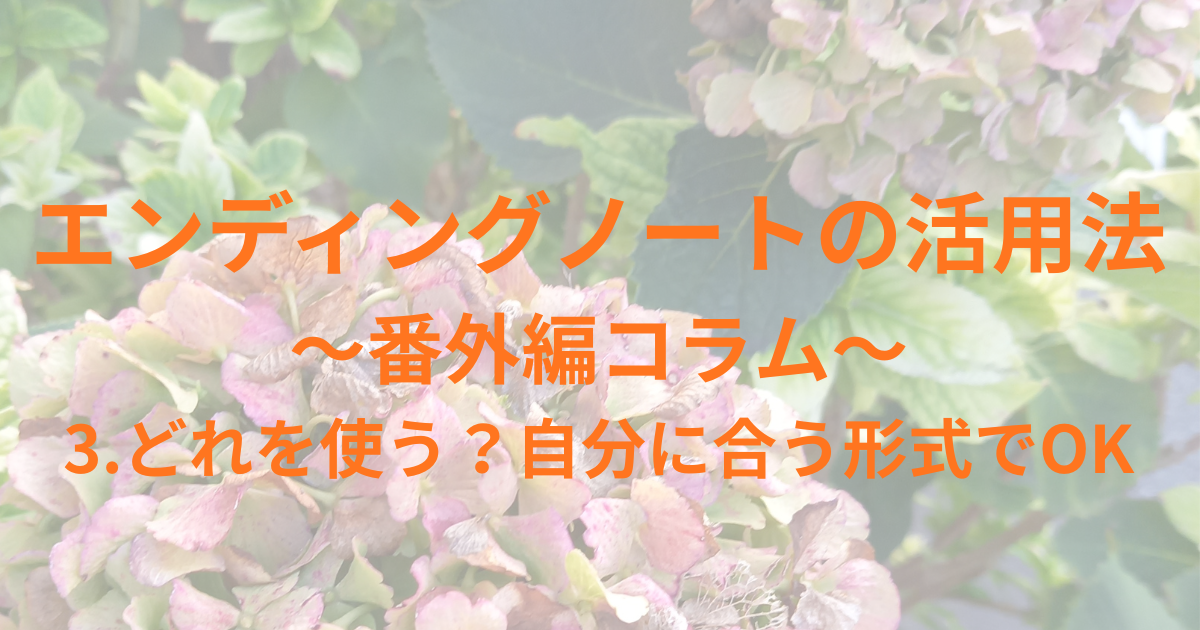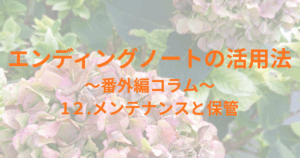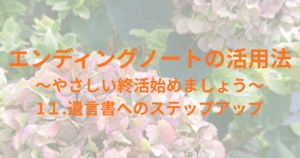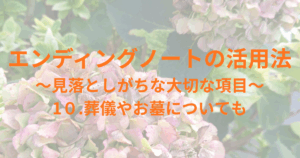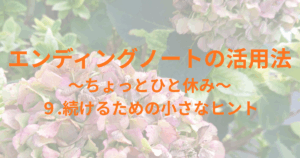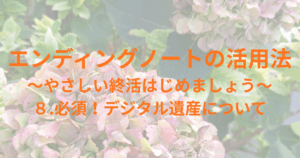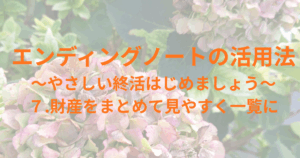今回は番外編として、エンディングノートの選び方についてお話してみようと思います。
いざ「エンディングノートを書いてみよう」と思っても、実際に探してみると種類がたくさんあって迷ってしまいますね。
そこで「どんなノートを使えばいいの?」という悩みが出てきて、エンディングノートを書く前に立ち止まってしまう…こんなお声を耳にすることがよくあります。
そんな迷いに、行政書士の視点から、使いやすさで選ぶヒントをお伝えします。
1.代表的なタイプを3つご紹介
エンディングノートは、自分の思いつくままに、これまでとこれからを自由に書き込んでいくためのノートですから、形式に正しいとか間違っているといった答えはありません。
何より、ご自分が書きやすい、使いやすい、書いていて楽しくなるようなものが良いと思います。
そして書き上がったときに達成感、満足感が得られるような形であれば、なお、良いですね。
⑴市販のエンディングノート
今は書店や文具店、インターネット通販でさまざまなエンディングノートが販売されています。
また、自治体で市民向けに配っていたり、銀行、保険会社などが顧客向けに無償で提供するといったものも多くあるようです。
まずは、そういった手軽に手に入るものを活用するのがひとつの方法です。
<メリット>
・項目が整理されていて、何を書けばよいか分かりやすい
・「財産」「医療」「家族」など見出しがついていて書きやすい
・デザインや紙質が色々あって選ぶ楽しみがある
<デメリット>
・項目が多すぎて途中で疲れてしまうことも
・一部だけ書きたいときには少し重たい印象
・すべて書き込めないと挫折感を味わいやすい
何もないところから始めようとすると、まず書く項目から迷ってしまうかも知れません。
そんなときには、あらかじめ書くべき項目が整理されている市販のエンディングノートから試してみるのがおすすめです。
「終活をしっかり形にしたい」「最初から形式がある方が安心」というしっかり派の方にも良いと思います。
⑵手帳・ノートで手作りタイプ
エンディングノートとして作られているものではなく、普通のノートや手帳などに、自分の書きたい内容だけをまとめていく方法です。
わざわざ探して専用のノートを購入しなくても、お手持ちのノート、使っていなかったバインダー式手帳など、何でも良いと思います。
「エンディングノートを買いに行く」「ネットで探してどれが良いか迷う」といったことがなく、思い立ったときにすぐ始められるのが、このタイプの一番の強みです。
<メリット>
・自分の書きたい項目だけに絞れる
・バインダー式なら後からページを増やしたり、差し替えたりできる
・気楽に始められる
<デメリット>
・書く項目を自分で決める必要がある
・書く順番や内容がバラバラになりやすい
・必要な情報が抜けてしまいやすい
デメリットとして挙げた点は、裏を返せばこのタイプの良い点にもなります。
「自由に書ける」「思いつくままにどんどん書いていける」「書きたいことだけ書けばよいので続けやすい」…こんなエンディングノートを求めている方におすすめの方法です。
行政書士としても、始めはどんどんノートにメモ感覚でまとめていただき、後から必要な部分を加えながら、遺言書などに反映させていく、という形は実用的だと思います。
⑶スマホ・パソコンのデジタルタイプ
最近では「エンディングノートアプリ」やWEB上で終活ノートを遺せるようなサービスも増えています。
これらはパソコンからだけではなく、スマホからも手軽に利用できます。
入力していくだけで、エンディングノートを作成することができるので、手書きが苦手とか、字を書くのに困難がある方には、とても良い方法だと思います。
先にお話しした、自治体で配布・販売されているエンディングノートも、ダウンロードできるようになっているものが多く、PDF形式であれば、PDF編集ソフトを使ってそのまま入力していくこともできるでしょう。
<メリット>
・スマホやパソコンからいつでも書ける
・修正や更新が簡単にできる
・画像や動画を残せるタイプもある
<デメリット>
・サービス終了やパスワード忘れのリスクがある
・財産に関する情報などの流出の危険がゼロではない
・家族がアクセスできない場合もある
※デメリットに挙げたうちの最後の「家族がアクセスできない場合がある」という点には、特に注意が必要です。
せっかく自分の希望や想いを伝えるために作ったエンディングノートを、スマホやパソコンのロックが解除できないために、家族が見られない、という可能性があるのです。
行政書士としてこの点への対応ポイントをお伝えするなら、「紙でバックアップ」しておく(つまり印刷しておく)、もしくは「ID、パスワードの控え」「ロック解除のパターンやパスワードの控え」だけでも残しておくといった対策をすると安心です。
このデジタルタイプは、「スマホやパソコンの操作に比較的抵抗がない」「情報はデジタルで管理したい」という方におすすめの方法です。
ご自分で書く、という作業が難しい方でも、今は音声で入力できるソフトがありますので、そんな方法を活用して、ぜひエンディングノートを始めていただければと思います。
2.組み合わせるのもアリです!
ひとつの方法を選んだとして、それをずっと使い続けなくてはならない、ということはもちろんありませんので、良いとこどりをして組み合わせていく、といった方法も良いでしょう。
⑴ノートとアプリの組み合わせ
簡単に書けるところや、メッセージのように手書きで残したいものはノートに、財産管理については煩雑なのでデジタルで、といった具合です。
⑵市販ノートの一部を利用して自作する
用意したエンディングノートの中で、書きやすそうなページだけをコピーして使い、あとは自分の書きたい項目で自由に作成するやり方。
この場合におすすめなのが、クリアファイルを綴じていくバインダー式のファイルを活用することです。
コピーしたページや、パソコンでダウンロードしたページ、もしくはご自分で自由に書いたルーズリーフなどを、クリアファイルに入れこんで、バインダーに綴じていくのです。
これならページごとの差し替えも、一部の修正も簡単に出来ますし、何よりクリアファイルであれば写真を入れたり、大事な手紙を入れたり、自分に関する資料をまとめておける便利さがあります。
3.まとめ
エンディングノートは「書き方」よりも「続け方」です。
タイプ別に例えるなら
・市販ノートタイプ:しっかり派
・手作りノートタイプ:自由派
・デジタルタイプ:スマート派
かなりおおざっぱな言い方ですが、どんな形を選ぶにしろ、あなたが一番書きやすい、続けやすい形で、とりあえず始めてみることが大事なのではないかと思います。
そして、いつかそのノートが「遺言書作りのきっかけ」となり、そのために役立つ「材料」になれば、それが一番の理想ですね。
行政書士わかぞの事務所では、遺言書や相続、終活のご相談をお受けしております。
もしもお困りごとやご心配、悩んでいらっしゃることがあれば、お考えがまとまらないままでも大丈夫です。
初回は無料でご相談をお受けしておりますので、お気軽にご連絡してください。
お問い合わせはお気軽にどうぞ
行政書士わかぞの事務所