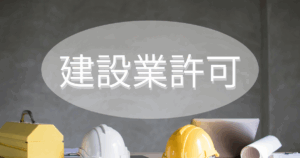【建設業という業種で営業するには、許可を受ける必要があります】
なぜなら、建設という業態は多くの工程があり、その工程ごとに関わる人・会社も多く、また発注する側にとっても金銭的に大きな負担となる取引だからです。
簡単に言えば、大きな影響力を持つ取引なので、しっかりした基準のもとで許可を得た人だけができるようにしよう、と言うことです。
その建設業許可について、どんな種類があって、どうすれば許可を受けられるのか、順を追って学んでいきたいと思います。
【建設業についての基礎知識】
今回は建設業法に出てくる言葉の定義を中心にまとめました。基本的なことばかりですが、しっかり押さえておきましょう。
1.建設業の定義
建設業法において建設業とは以下の通りです。
「元請、下請その他いかなる定義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業」
「請負」とは「当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約」を言います。
注意!!
建設業における「ある仕事の完成」とは「建設工事の完成」であり、業務委託や雇用、委任などの名目で交わされる契約でも、実質的に報酬を得て建設工事の完成を目的として交わされる契約はすべて建設工事の請負契約とみなされます。
2.建設業者の定義
ひとくちに「建設業者」と言っても、法律上の定義では建設業法に決められた建設業の許可を受けて建設業を営む「許可業者」を指します。
そして許可を受けずに建設業の営業を行う事業者は、「建設業を営むもの」とされます。
(建設業の許可については、また別の記事で解説します。)
3.発注者と請負人
はじめに建設工事を注文する人を「発注者」と言います。
その発注者から直接建設工事を請け負う人を「元請」といいます。
そして元請からさらに仕事を請け負う人が「下請」です。
つまり「元請」は「下請」に仕事を注文するわけですが、この「元請」は発注者とは言いません。
あくまで他から請け負った工事以外を注文するのが「発注者」となります。
4.許可の必要のない建設工事
建設業者とは「許可業者」だと言いましたが、では「建設業を営むもの」とされる事業者が行う工事とは、どんな建設工事なのでしょうか?
建設業許可を受けなくてもできる建設工事は「軽微な建設工事」と呼ばれます。
「軽微な建設工事」
⑴1件の請負代金が500万円未満の工事
⑵建築工事一式(総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事)で、1件の請負代金が1500万円未満の工事、または木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
軽微な建設工事の限度を超える工事を請け負う事業者は、建設業許可を受けなくてはなりません。
そして許可が必要な建設工事については、工事の種類によって29種類の区分があります。
以上、建設業法に出てくる基本的な用語の定義を解説いたしました。
イチから建設業許可について知りたい、という方に向けて、平易な言葉で少しずつ一緒に学んでいければという趣旨で構成しております。
肝心の建設業許可に関しては、続けて記事を公開していきますので、お読みいただければ幸いです。
建設業許可に関するお問い合わせはこちらへ
行政書士わかぞの事務所