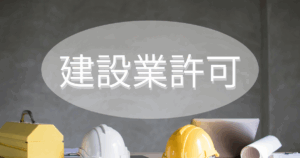【建設業の許可は建設工事の種類ごとに区別があります!】
街で見かける工事現場には、大きな工事現場と比較的小規模な工事現場、いろいろあります。大きな建設工事では、関わる下請け業者の数も増え、動く金額も大きくなってくるのは当然ですね。
そして比較的小規模の、一般住宅の工事などは、許可の必要ない「軽微な建設工事」の集合体になる場合もあるようです。
では、いわゆる許可業者として建設工事を請け負う場合、どんな許可が必要になるのか、順番に確認してみましょう。
【建設業許可についての基礎知識】
今回は、建設業許可にはどんな種類、区分があるのか。それを解説していきます。
1.建設業許可が必要なのは?
まずは許可を取らなくてはならないのは誰なのか?ということですが、それは「元請人」と「下請負人」どちらも必要になります。
よくある勘違いパターン①
「元請さんが許可を持ってるから、下請の自社は許可がなくても大丈夫だろう」
これは違います。
「軽微な建設工事」のレベルを超えた工事を請け負うのであれば、下請であっても許可を取らなくてはなりません。
※許可を受けずにいると無許可営業として罰せられます。この場合、3年以下の拘禁または300万円以下の罰金に処せられることになります。
2.建設業の種類
建設業の許可、と言ってもひとつではなく、建設工事の種類によって、それぞれ対応する許可の種類が決まっています。
2つの一式工事と、27の専門工事に分かれており、営もうとする建設工事の種類によって、適した許可を取らなくてはなりません。
ここでよく確認しておかないと困ったことになります。
「違う種類の許可を取ってしまって、請け負った工事ができなくなった」
これは実際にもありえるケースです。
この場合、新規に許可を取り直すとしても、1~2ヶ月はかかってしまうので、その間、請け負った仕事ができない、という深刻な状況になりかねません。
自分がやろうとしている工事には、どの許可が必要なのか、判断がつきかねる場合は官公庁の窓口で確認するなどして、正確に判断するようにしましょう。
3.2種類の一式工事
土木一式工事→土木工事業の許可
建築一式工事→建築工事業の許可
一式工事とは、総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物または建築物を建設する工事で、専門工事を組み合わせて建設工事を行う場合の業種です。
4.専門工事の区分
列挙してみます。
大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・レンガ・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業。
以上の27種類に分かれているのが専門工事です。
よくある勘違いパターン②
「一式工事の許可を取ってるから、専門工事なら何を請け負ってもいいんだろう」
これは違います。
一式工事と専門工事はあくまで別個のものとしてとらえる必要があります。
一式工事の許可を持っているからと言って、包括的にすべての専門工事ができるわけではないのです。また専門工事の許可を別で取らなくてはいけません。
今回、解説した工事の種類による区分以外に、営業所の数や所在地による区分、請け負う工事の代金による区分もあります。
次回の記事で、そちらについて解説したいと思います。
建設業許可についてのお問い合わせはこちらへ
行政書士わかぞの事務所