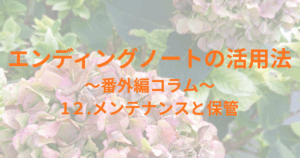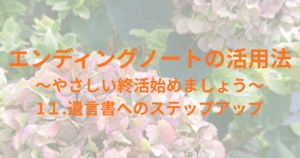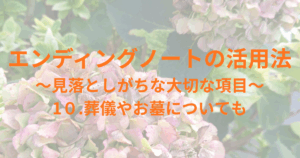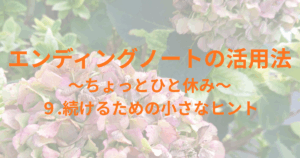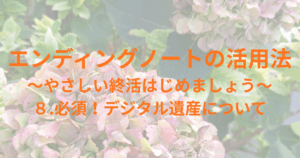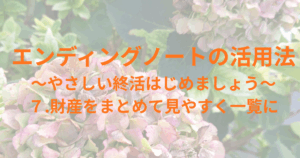遺言を残すということ
「遺言」と聞いて、自分にはまだまだ関係ないもの…と思う方。
そのうち準備すれば良いか…と先延ばしにしがちな方。
もしくはそもそも遺言を残すほどの財産は自分にはないから必要ない…と思う方。
本当にそうでしょうか?
たとえ大きな財産などなかったとしても、生きてきた年数の分だけ、関わった人間の数だけ、あなたのこれまでの行動や想いが、生きた証となって残されるのです。
そんな証がある日突然、あるじ不在の宙ぶらりんの状態で放り出されたら、どうなるでしょうか?
遺された家族は、大切なあなたの生きた証をどうやって受け継いだら良いのか、あなたの意思を直接聞くことも出来ずに、戸惑い迷い、時には家族同士で争うことにもなりかねません。
亡くなったあなたを悼み、恋しく想うその時間に、無用な争いや行き違いによる後味の悪さ、または予想外の手間と労力に疲弊すると言った辛い経験をさせないで済むように、今、考えてみませんか。
遺言は一度書いたらもう終わり、ではありません。何度でも修正出来るのです。
伝えたい想いが変わったら、残したいものが増えたら、いつでも何度でも書き換えられるのです。
ですから…
まだ必要ない、書き方がよく分からない、私とは関係ないもの…と思っている方へ。
「遺言はあなたが大切な家族に遺していける、最後の贈り物」です。
誕生日、年の始め、結婚記念日…タイミングはいつでも構いません。まずは自分の想いを書き出してみましょう。
遺言を残すことでできること
1.財産の相続内容を指定出来る
まずは残された財産の相続について、誰に、何を、どのくらいずつ相続させるかという指定ができます。
民法では、法定相続人の範囲、及びその法定相続分が決められていますが、遺言による指定相続は、法定相続より優先されるのです。
2.受遺者の指定ができる
法定相続人は法律上の血族に限られます。
しかし、それ以外でもお世話になった人、長年苦楽を共にしたパートナー、事業を継承してくれる人…など、ぜひこの人に財産を残したい、と考えることはあるはずです。
そんな時、遺言で「受遺者」の指定が出来るのです。
3.相続人の廃除ができる
反対に血族であっても、この人にだけは残したくない、継いでほしくない…といった相手がいた場合。
遺言により廃除の意思表示をすることが可能です。その際には、必ず遺言執行人の指定をしておきます。そうして相続が発生した後に、遺言執行人が家庭裁判所に廃除の申立てを行う、という流れになります。
ただし廃除が認められる要件は、かなり厳しくなっているのと、廃除した相手に子どもがいた場合は、その子が代襲相続と言った形で相続人となることがあります。
4.遺言執行人の指定ができる
遺言としてしたためた自分の意思を、確実に現実にしてくれる人として、遺言執行人を指定することが出来ます。
遺言を残したはいいものの、ちゃんとその通りにしてくれるのだろうか?自分の思う通りになるのだろうか?
そんな不安も、遺言の中で遺言執行人を指定しておくことで解消されます。
5.後見人の指定ができる
例えば財産を相続する家族の中に未成年の子がいたとします。
そんなとき、その子が成人するまで財産管理を委ねる後見人を指定することが出来るのです。
6.認知ができる
婚姻関係になかった女性との間に子どもがいた場合、その子を遺言によって認知することが出来ます。
遺言書を作成した方が良い場合
では、どんな場合に「特にこんなケースは遺言書を作成した方が良い」と考えられるのでしょうか?
- 夫婦の間に子どもがいない
- 再婚して連れ子がいる
- 内縁の夫、妻がいる
- 身寄りがない
- 相続人が大勢いる
- 相続手続きを簡単にしておきたい
- 家族以外の人に財産を残したい
もしも当てはまるという方は、積極的に遺言書を書くことを考えてみましょう。
遺言書の種類
1.自筆証書遺言
遺言書の全文、日付、氏名が全て自筆で書いてあり、押印されていることが条件です。
費用が掛からず、手軽に作成できる反面、要件を満たさない形式であった場合、無効となる恐れがあります。
また保管は自己の責任となるため、遺失や改ざんのリスクがあり、相続開始後はまず、開封前に裁判所での検認という手続きが必要になります。
2.公正証書遺言
公証役場において、遺言の形式、内容、適法性などを公証人が確認し証明してくれるものです。
この公正証書遺言という形であれば、無効になることはありません。
公証役場において保管してもらえるため安心ですが、費用が掛かり、証人が2人必要となります。
自筆出来ない方でも遺言書を作成することが出来ます。
3.秘密証書遺言
遺言の内容を誰にも知られずに作成する方法です。全文が自筆でなくてもかまいません。
公証人の目の前で封印した遺言書を提出し、それが本人の遺言書であると認証を受けるだけなので、公証人が内容を確認するわけではありません。
ですので内容に不備があると、法的に無効になってしまうこともあり得ます。
公証役場での手続きに費用が掛かり、証人が2人必要となります。
保管は自己で行うので、遺失、改ざんのリスクはあり、裁判所での検認手続きも必要です。
いかがでしょうか。これらの中で、もっとも推奨されるのはやはり公正証書遺言です。
せっかく遺言を作成するのですから、きちんと条件を整えて、自分の意思が生かせるようにしておくのが、残される家族のためであり、また自分が生きる上でも安心を得られる最良の方法ではないでしょうか。
まとめ
ここまで読んでいただいて、遺言書を書くことに対するハードルが少しは低くなりましたでしょうか?
難しく考えずに、自分の希望を書いてみる、自分の願いを文字にしてみる、という感じで書き始めてみるのも良いですね。
そして、きちんとした形で残しておこうとなったとき、形式や書き方、内容などについてアドバイスが欲しい、ということであれば、専門家に相談してみるのも良い選択肢だと思います。
行政書士は、相続人の調査から相続財産目録の作成、遺言書作成に関するアドバイス、遺言執行人としての遺言執行までトータルでお手伝いすることができます。
街の身近な法律家である行政書士を、ぜひ活用してみてください。
お問い合わせ、ご相談はお気軽にどうぞ。
行政書士わかぞの事務所