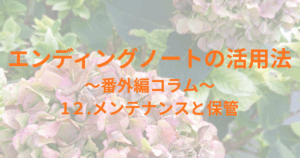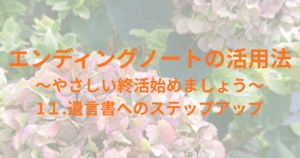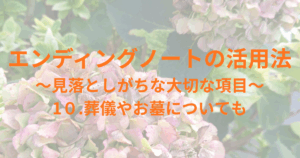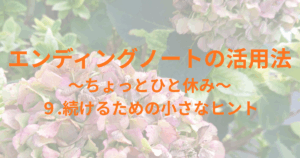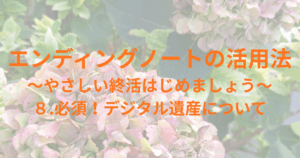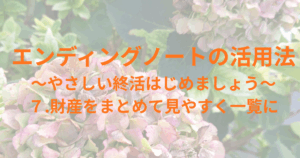「まだまだ元気だし、遺言書なんてそのうちに必要になったら書いたら良い」
「ウチは家族みんな仲が良いし、子どもたちも上手くやってくれるだろうから遺言書なんていらないよ」
「前々から相続については長男に話してあるから、私は遺言書なんて書かなくても大丈夫だろう」
……本当にそうでしょうか?
どんなに家族仲が良くても、人には色んな考えや思いがあり、状況も日々変わっていくのです。
どんなに詳しく伝えてあったとしても、伝えられたのがたった一人だったら、他の全員は納得するでしょうか?
また、今日は元気でも、明日はどうなっているか分かりません。これは老いも若きも同じことです。いつどうなるか、ということは誰にも分からないのです。
「その時」は突然訪れるかもしれません。何の準備もなく、その時がやってきてからでは遅いのです。
あなたの意思をきちんとした形で示し、周りが納得する形で残しておけば、たとえその時が「明日」であろうが、「1年後」であろうが、「10年後」であろうが、残された家族があなたの意思を推し量ろうと悩むことも、ましてや争うこともなくて済むはずです。
そして自分が生きている間も、ちゃんと自分の意思が家族に伝わるようにしてあると思えば、これほど安心出来ることはないでしょう。
遺言書を作成した方が良いのはどんな場合?
誰かが亡くなった後に遺された財産(遺産)は、故人の遺言書がない場合、法定相続分に従って、もしくは相続人同士の話し合いによって、分割の仕方が決まります。
それで問題ない場合もありますが、次のような時は遺言書がなければ自分の意思は反映されません。
「法定相続人以外に遺産を残したい相手がいる」
「不動産など特定の財産を特定の相続人に残したい」
「相続人の数が多い」等……
以下、具体的に遺言書を作成すべき場合を挙げてみますが、その前に「法定相続人」の考え方についてざっとおさらいをしておきましょう。
<配偶者> 常に相続人となります。
<一定範囲の血族>
第1順位 被相続人の子ども、既に死亡している場合はその子ども(孫)か孫(ひ孫)
第2順位 被相続人の父母、既に死亡している場合は祖父母
第3順位 被相続人の兄弟姉妹、既に死亡している場合はその子ども(甥、姪)
<第1順位>がいなければ<第2順位>に、<第2順位>がいなければ<第3順位>に…というように相続人の地位が移っていきます。
こんな場合は遺言書が必要です!
1.夫婦の間に子どもがいない
この場合、配偶者が100%遺産を相続するものだと勘違いしがちです。
しかし、子どもがいなければ、配偶者にとっては義理の父母か祖父母、それがいなければ義理の兄弟姉妹か甥姪と遺産を分割することになります。
生前の関わり方によっては、行き来の少なかった相手と遺産分割協議をすることは、配偶者にとっても少なからぬ負担となるでしょう。
2.再婚した相手に連れ子がいる
被相続人と養子縁組をしていれば実子と同様の相続分がありますが、そうでない場合は法定相続人にはなりません。連れ子にも相続させたい場合は遺言書が必要です。
また、以前婚姻関係にあった相手との間に子どもがいる、認知した婚外子がいる、等の場合も全ての子どもに相続の権利がありますから、争いにならないよう遺言書を残した方が良いでしょう。
3.内縁の夫、妻がいる
配偶者、とはあくまで法律上の正式な配偶者のみを指します。
いくら長い間人生を共にした相手であっても、法律上の夫婦でなければ配偶者とはならないのです。
内縁の相手に相続させたい場合は遺言書が必要です。
4.身寄りがない
独身で、子どももなく、親兄弟、甥姪もいない場合は相続人がいないということになります。
そうした場合、故人の財産は国庫に納められることになります。
自分の財産をどうしたいか、希望があるならば遺言書を作成しましょう。
5.相続人が大勢いる
自分の子ども以外に孫も代襲相続人となる場合、兄弟姉妹が大勢いて、その中の幾人かは亡くなっており甥姪が代襲相続人となる場合…など相続人の数が多いときは、なかなか遺産分割協議がまとまらない可能性が高くなります。
大勢での話し合いがスムーズに進むように、遺言書を準備しておきましょう。
6.家族以外の人に財産を残したい
法定相続人とは配偶者と一定範囲の直系血族に限られます。
それ以外に、とてもお世話になった相手やぜひ自分の財産を譲りたいと考える相手がいるのであれば、遺言書で遺贈の意思を示しましょう。
例えば献身的に介護してくれた息子の嫁、事業で苦しい時に助けてくれた友人知人、自分が力を入れて活動していた団体等…遺言書がなければ、当然と財産を譲ることは出来ません。
7.財産に不動産が多い
現金や株式等、分割しやすい財産であれば良いのですが、不動産は半分ずつ、または1/3ずつ分け合う…といった事が出来ませんね。共有、というやり方も後々の管理や処分に時間や手間がかかるでしょう。
不動産の遺産分割として、売却してその代価を分割することも出来ますが、まだ家族が暮らしている家と土地であればそうも行きません。また山林などすぐに売れるとは限らないものもあります。
どんな分割方法で、分割割合でと遺言書で指定することで、残された家族の負担はぐっと減るはずです。
8.マイナスの財産がある
相続というのはプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も等しく相続人に引き継がれます。
生前に清算しきれなかった借入金や、保証債務など、相続人に背負わせたくないものがある場合は、遺言書に全て記しておくことで、相続が発生したときに相続放棄や限定承認などの手段が速やかに取れるようになります。
まとめ
いかがでしょうか?何かご自分が当てはまる、と思われたケースはありましたか?
遺言書とは、自分の意思と希望を家族に伝えるものではありますが、それと同等かそれ以上に、残される家族が穏やかに「相続」という波を乗り切るための大きな船となるものなのです。
遺言書があることにより、家族はあなたの想いを受け取ることができ、あなたは言葉を発することが出来なくなったとしても、想いを伝えることが出来るのです。
遺言書が必要かどうかについて、よく分からない、誰かに聞いてみたい、という方はぜひ専門家のアドバイスを受けてみてください。
遺言書作成については、行政書士もご相談を承ることができます。
なかなかご自分の家の事情について、友人や知り合いには話しにくいものですが、守秘義務のある行政書士であれば、安心してご相談できると思います。
第三者である専門家の立場から、適切なアドバイスを受けることにより、漠然とした不安を抱えている現状から、一歩前に進むことが出来るでしょう。
お問い合わせ、ご相談はお気軽にどうぞ。
行政書士わかぞの事務所