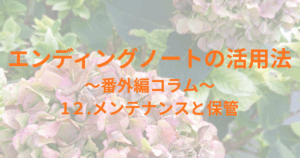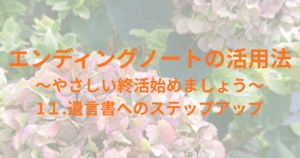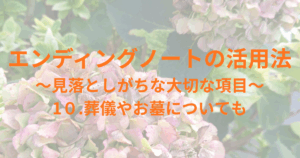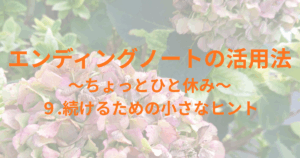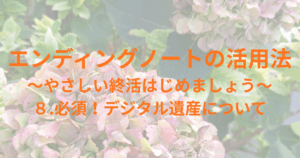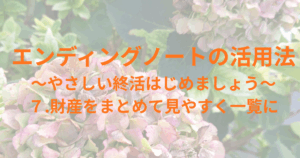近年、「終活」という言葉が広まり、自分や家族の将来について考える方が増えています。その中で、「墓じまい」という言葉を耳にする機会も多くなりました。
「ご先祖様のお墓をなくすなんて、罰当たりなのでは?」
そう感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、現在の日本では、お墓を維持し続けることが困難な状況に直面している家庭が増えています。「墓じまい」は、決してご先祖様を軽んじる行為ではありません。むしろ、これから先も子や孫が安心して手を合わせられるように、大切な人を未来へつなぐための前向きな選択肢なのです。
今回は、「墓じまい」とは何か、その背景から具体的な手続き、そして新しい供養の形まで、分かりやすくお伝えします。
「墓じまい」とは? 具体的な意味を解説
「墓じまい」とは、現在あるお墓からご遺骨を取り出し、その墓石を撤去して更地にし、墓地の管理者へ返還することです。
かつては「お墓を代々守っていく」ことが当たり前でしたが、遠方に住んでいてお墓参りが難しい、後継者がいない、経済的な負担が大きいなど、様々な理由からお墓を守り続けることが困難になるケースが増えています。
「お墓が遠くて、なかなか帰省できない」「子どもに負担をかけたくない」といった悩みをお持ちなら、今あるお墓をどうするのか、一度立ち止まって考えてみる時期に来ているのかもしれません。
なぜ今、「墓じまい」が増えているの?その背景とは
墓じまいが増えている背景には、どんな事情が関係しているのでしょうか。
1.少子高齢化と核家族化
「お墓を守る」という役割は、これまでその家の長男が引き継ぐのが一般的でした。しかし、少子化によって後継ぎがいない家庭が増え、また、核家族化が進んで親子が離れて暮らすことが多くなったため、お墓の管理が難しくなっています。
2. 地方から都市部への人口移動
就職や結婚を機に、故郷を離れて都市部で生活する人が増えました。年に数回のお墓参りも、移動時間や費用を考えると大きな負担となります。結果として、何十年もお墓参りに行けていない、というケースも珍しくありません。
3. 供養に対する考え方の多様化
「家のお墓」という伝統的な考え方だけでなく、「夫婦二人のお墓」「永代にわたって供養してもらうお墓」「自然に還るお墓」など、個人の価値観に合わせた様々な供養の形が受け入れられるようになりました。
4.経済的負担
お墓の維持管理には、年間管理料や修繕費など、継続的な費用がかかります。この負担を軽減したいと考える方も少なくないでしょう。
墓じまいの具体的な流れと手続き
墓じまいは、以下の流れで進めるのが一般的です。複雑そうに思えますが、一つずつクリアしていけば大丈夫です。
まず最も大切なのは、家族や親族に「墓じまい」についてきちんと相談し、理解を得ることです。個人や先祖に対する思い入れや感情はそれぞれです。後々のトラブルを避けるためにも、全員が納得できる合意を得てから次のステップに進みましょう。
墓じまい後のご遺骨をどこに納めるのか、新しい供養先(改葬先)を決めます。
永代供養墓や納骨堂、樹木葬など様々な選択肢があります。
現在お墓がある寺院や霊園に、墓じまいをしたい旨を伝え、必要な書類や手続きについて確認します。場合によっては、これまでのお礼として「離檀料(りだんりょう)」が必要となることがあります。
現在お墓がある自治体で、「改葬許可証」を取得します。
「改葬許可証」とは、ご遺骨を移動させるために必要な許可で、現在ご遺骨が埋葬されている場所の自治体が発行する書類です。
ご遺骨を取り出す前に、お墓を単なる「モノ」に戻すための「閉眼供養(へいがんくよう)」や「魂抜き」と呼ばれる儀式を行います(任意)。その後、石材店に依頼してお墓を撤去し、更地に戻します。
ご遺骨を新しい供養先に納骨し、必要であれば「開眼供養}(新しいお墓に故人の魂を入れる儀式)や納骨式を行います。
気になる費用とトラブルを避けるための注意点
墓じまいの費用は、お墓の大きさや場所、新しい供養先によって大きく変わります。主な費用の内訳は以下の通りです。
1.費用内訳
閉眼供養のお布施:3万円〜15万円程度
お墓の撤去・解体費用:1平方メートルあたり10万円程度
離檀料:慣例としてお寺に支払う費用。相場はありますが、事前に確認が必要です。
新しい供養先の費用:永代供養墓や納骨堂は、タイプによって数十万円〜数百万円と幅があります。
行政手続きの費用:改葬許可証の発行手数料などの費用で、数百円~数千円程度。
その他諸経費:ご遺骨の運搬料、専門家への相談料、現地までの交通費などが含まれます。
新しい遺骨の供養先をどこにするかによって、墓じまい全体にかかる費用は大きく変わってきます。しかし、一般的には数十万から百万円以上かかることが多いようです。
いずれにしろ事前に見積りを取って、よく確認しながら計画的に進めることが重要です。
2.注意すべきポイント
親族とのコミュニケーション不足によるトラブル
墓じまいは一度行うと元には戻せません。親族間で「聞いていない」という事態にならないよう、事前の丁寧な説明と合意形成が最も重要です。
寺院との関係性
寺院によっては、檀家をやめること(離檀)に対して、トラブルに発展することもあります。できるだけ早めに、誠意をもって相談しましょう。
第三者の活用
必要であれば、行政書士や終活カウンセラーなど、墓じまいの専門家に相談し、客観的なアドバイスを得ることも有効です。
墓じまい後のお骨の供養方法と選択肢
墓じまい後のお骨は、新しい供養先に納めることになります。いくつかの代表的な選択肢をご紹介します。
永代供養墓:霊園や寺院が管理・供養を代行してくれるお墓です。後継ぎがいなくても安心です。
納骨堂:屋内の施設にご遺骨を安置します。天候に左右されずお参りできるのがメリットです。
樹木葬:墓石の代わりに樹木をシンボルとして埋葬する方法です。自然志向の方に人気があります。
散骨(海洋散骨):ご遺骨を粉末状にして、海などに撒く供養方法です。
手元供養:自宅に小さな骨壺を置いて供養する方法です。
これらの選択肢から、家族の想いやライフスタイルに合った供養の形を選びましょう。
まとめ
「墓じまい」は、決してご先祖様との縁を断つことではありません。
今生きている私たちにとって、故人との関係性や家族の歴史に向き合う大切な機会ともなるのです。
そう考えると、墓じまいは終着点ではなく、大切な人を未来の世代へと受け継ぐためのひとつの選択肢だということができると思います。
もしも専門家のアドバイスが欲しいという場合は、お近くの行政書士にお気軽にお問い合わせください。きっとお力になれることがあるはずです。
お問い合わせ、ご相談はお気軽にどうぞ。
行政書士わかぞの事務所