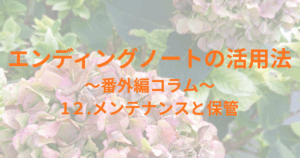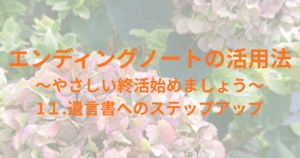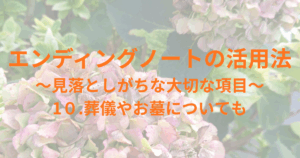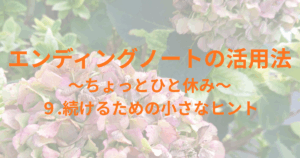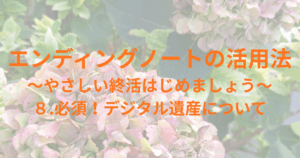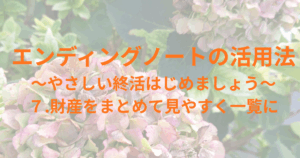世界トップクラスの長寿国、日本。長生きは喜ばしいことですが、それも健康でしっかりしていればこそ。誰でも、いつかは歳を取り、自分一人で何もかもは出来なくなりますよね。
そんな時に頼る相手が大勢いる人は心配ないでしょうが、身寄りがいない、家族と疎遠だ、頼れるような友人もいない…こんな状況にいる人。近頃よく耳にする「おひとりさま」は、いざという時、どうしたら良いのでしょうか。
ここでは、独り身の暮らしをどう支えるか、という視点から、厚生省が打ち出した「高齢者等終身サポート事業」のうち、死後事務に関して解説してみたいと思います。
高齢者等終身サポート事業とは
身内に頼れない高齢者への公的な支援制度の創設を目指して、厚生労働省が2024年に始めた事業で、全国の自治体に支援制度の試行を呼び掛けています。
さらに民間の事業者に対しては高齢者等終身サポート事業者ガイドラインを策定し、高額な契約を結ばされる、契約した後に倒産する…などのトラブルをなくしていこうとするものです。
サポートの中身としては主に3つに分けられます。
- 1.日常生活支援
-
緊急時の親族への連絡や、一人暮らしの見守り、買い物の代行などを行います。
- 2.身元保証
-
施設への入所、入院時などに求められる身元保証人の役割を引き受けます。
- 3.死後事務
-
遺体の引取、葬儀、埋葬、各種届出、遺品整理などを行います。
死後事務委任とは
本人が亡くなった後に発生する各種手続きを、信頼できる第三者に委任する契約です。
おもな死後事務の内容としては次のようなものが挙げられます。
・葬儀・火葬・埋葬の手配
・死亡届の提出
・遺品整理、住居の引き渡し
・公共料金や契約の解約手続き
・関係者への連絡(親族、施設、病院など)
・墓地管理、供養の手配
・遺言執行や相続手続
・入院費や施設費、賃料の支払い
家族や頼れる身寄りのない人にとって、自分の死後に残されるであろうさまざまな手続きを、誰かが代わりにやってくれる、という安心感は大きいのではないでしょうか。
民間の事業者の他、一般社団法人、社会福祉協議会、NPO法人、行政書士、司法書士、などがサポートを提供していることが多いようです。
死後事務委任を利用するには
死後事務委任は契約によります。
そしてその契約は公正証書として保管する必要があります。
この死後事務委任契約を確実に履行するためには、合わせて公正証書としておく方が良いでしょう。
利用したいサービスと提供されるサービスが一致しているか、金額的に無理はない範囲か、どこまでの手続きをカバーしてくれるのか、よく確認して納得できたら、その内容を契約書に書き入れてもらうようにしましょう。
費用としては、一括して預託金として支払う方法、死後に下りる少額短期保険を充てる方法、銀行に専用口座を作りそこに資金を入れておいて、死後事務が発生したらそこから支払うようにしておく方法等が考えられます。
選ぶときに気を付けるポイント
さまざまな事業者が、さまざまなサービス内容を提供しています。
その中から、自分に必要なものだけを見極め、自分に合ったサービスを選ぶために、どんなことに気を付ければ良いのでしょうか。
・要望の整理…自分のしてほしいこと(希望)を明確にする。
・支払い能力の見極め…支払方法、金額等が自分の資産状況に照らし合わせ適正かどうか検討する。
・サービス内容の確認…事業者の出来ないことをよく確認して、納得してから契約書に残しておく。
・契約後も考えて…死後事務委任契約を結んだことを書面に残し、緊急連絡先等と共に分かりやすいところに保管する。契約内容の変更や解約の手続きについて説明を受け、確認しておく。
やたらと不安をあおったり、高額過ぎるサービスを勧めてくるような事業者は、当然ですが避けた方が無難です。
契約に関して迷いや不安がある場合は、消費生活センターに相談してみると良いですね。
まずは話をじっくり聞いてみて、焦らないことです。自分が納得するまでは契約しない。そして自分一人では決めかねる場合は、第三者の意見を求めてみる。
そうすれば、無理な契約を結んで後悔する、といったことは避けられるのではないでしょうか。
まとめ
おひとりで暮らしていると、色んな不安が押し寄せてくることがあるかも知れません。
特に死後に関しては、自分ではどうすることもできませんから。
その点、死後事務委任契約を結んでおけば、死後に誰かに迷惑をかけることはなくなります。
子どもや孫に負担をかけたくない、という希望も叶えられます。
大きな安心を手に入れることで、今を前向きに過ごせるようになると思います。
死後事務委任に関しては、行政書士にもご依頼いただくことができます。
相続手続、遺言執行、契約書・遺言書の作成、各種契約の解約、名義変更手続き…死後に発生する事務のほとんどを担うことができますので、もし死後事務委任に関して聞いてみたいという場合は、ぜひお近くの行政書士を活用してみてください。
お問い合わせ、ご相談はお気軽にどうぞ。
行政書士わかぞの事務所